やっと読み終えた。「教員の『働き方改革』はなぜ進まないのか」である。大阪大学の高橋哲教授の編著で、高橋氏を含め、8人の専門家による本である。結論から言えば、教育行政に関わる教育委員会関係者も含め、校長・教頭などの管理職、そして全ての教職員が読むべき本だろう。「働き方改革」がなぜ進まないのか、あらゆる方向から切り込まれているとともに、海外(取り上げられているのは、アメリカ、韓国、ドイツ、イギリス)の教員の労働条件の決定システムが紹介されているのはとても勉強になった。
高橋氏が終章でまとめているように、教員定数の見直し、「乗ずる数」の見直し、そして、厚労省が行っているように公労使の三者による協議団体の設置は、重要だろう。海外の教員の労働条件決定システムを読んでみると、教員側=労働者側の代表と教育行政の交渉で行われていることが分かった。高橋氏が指摘するように、今回の中央教育審議会の特別部会のメンバー構成を見れば、公労使の三者のうち、労の代表がいないことは明確である。この書の「教員の『働き方改革』はなぜ進まないのか」の分析の中で、唯一と言っていいほど抜けているのが、
「それならば、なぜ日本では『労』の代表が抜けているのか」
という問題だろう。ここに切り込まなくてはいけない。
教職員の労働組合組織としては、日教組と全教がある。連合系の日教組と共産党の影響下にある全教である。日教組の組織率は、2024年10月時点で48年連続して低下し、18.8%と過去最低を更新している。他の組織を含めた加入率は、26.8%で49年連続の低下なのである。組織化されていない教員が圧倒的に多いのだ。これでは、「労」の代表とは呼べないだろう。
なぜ、これほど組織率が低下しているのか。学校のブラック化が叫ばれ、教員不足が問題視されているのだから、日教組をはじめとした労働組合の組織率が伸びてもおかしくない。しかし、低下傾向に歯止めがかからないのだ。その原因は、教職員の組合組織への信頼が得られていないからである。
過去、日教組は、vs文部省という構図の中で、労働条件よりも、様々な政治的課題をメインに労働運動を展開してきた。それが教職員の組合離れに拍車をかけたのだ。日教組は、もう一度原点に戻って、教員の労働条件の改善に向けた方針を全面的に打ち出すべきではないか。
この間、度々マスコミでも教員の働き方改革の問題が取り上げられて来たにもかかわらず、「労」の代表である日教組の意見がほとんど取り上げられてこなかった。それは、教職員組合が、日教組と全教に分裂していることも大きな原因がある。一つだけを取り上げれば、もう一つはどうなのだという摩擦をもたらすからだ。
とにかく、もう一度教職員組合は原点に戻り、教職員の信頼を得るところから始めなければならない。この本の中で、この分析が無かったのは、残念である。
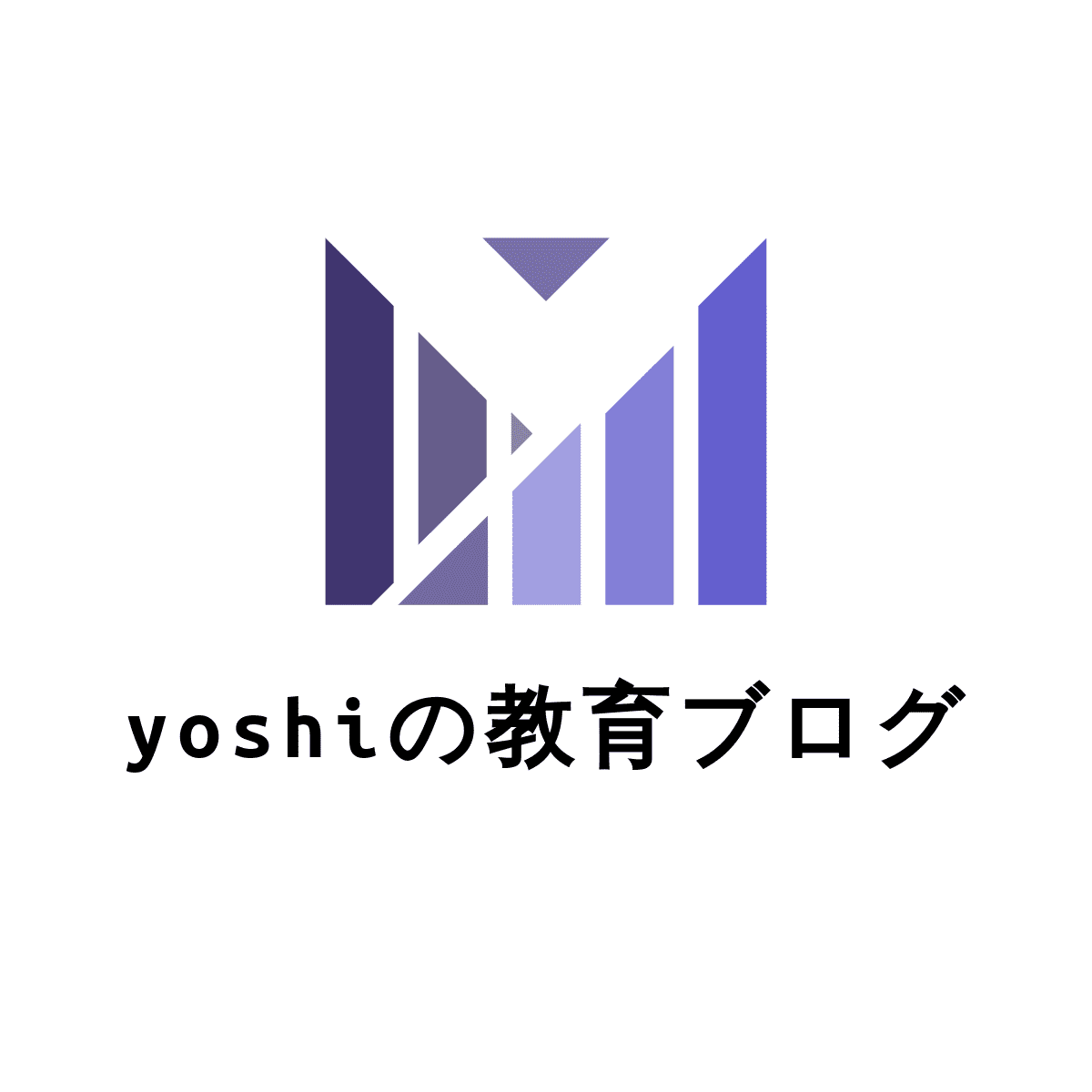
コメントを残す